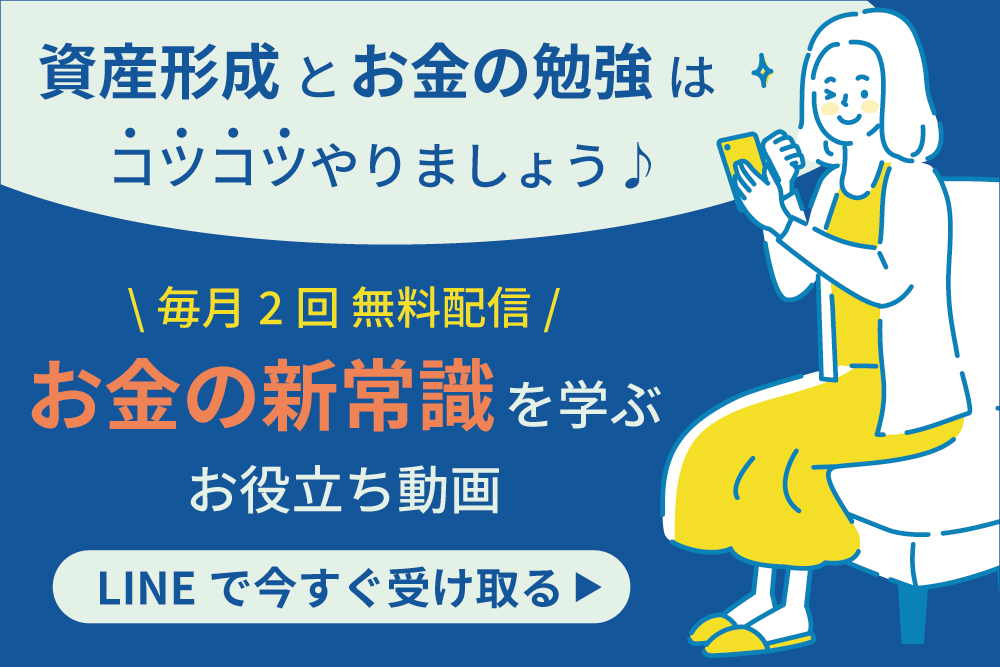個人年金保険は、老後の生活資金を準備するための重要な手段ですが、
受け取り方法や税金の仕組みについて正しく理解しておくことが大切です。
今回は、具体的な契約例をもとに、支払保険料から受け取り方法、
税金の計算までをわかりやすく解説します。
個人年金保険とは?
個人年金保険は、一定期間保険料を支払い、
満期後に年金形式または一括で受け取ることができる保険商品です。
老後の生活資金を計画的に準備する目的で利用されることが多く、
「貯蓄が苦手な人」でもコツコツ積み立てられる点が特徴です。
支払保険料と受取金額の実例
今回紹介する契約例では、65歳から10年間に
わたって年金を受け取る「確定年金」です。
•支払期間: 平成3年11月から令和元年11月まで29年間。
•支払保険料: 年払いで30万3,606円(医療特約分を除く)総額880万4,574円。
•受取金額: 毎年180万円ずつ10年間で総額1,800万円。1800万円÷880万円×100%=204%
この契約は、当時の予定利率が5.5%と非常に高く、
現在の低金利ではこのような条件の商品はほぼ存在しませんので
加入していてよかった例です。
3つの受け取り方法
では、この1800万円を実際に受け取る際の方法についてご説明いたします。
個人年金保険には以下の3つの受け取り方法があります。
それぞれの特徴とメリット・デメリットを見ていきましょう。
1.65歳から10年間にわたって年金形式で受け取る
•毎年180万円ずつ10年間にわたり受け取り、総額は1,800万円。
•計画的に資金を活用できる点がメリット。
•税金は「雑所得」として課税されます。
2.65歳で一括受け取り
•一括して1,488万6,537円を受け取る(将来価値に割引されるため減少)。
•税率が低い「一時所得」として課税されます。
•まとまった資金が必要な場合に適していますが、総額は減少します。
3.70歳から10年間にわたって年金形式で受け取る
•5年間遅らせることで利回りが上乗せされ、毎年225万743円ずつ10年間で総額2,250万7,430円。
•最も高い総額となり、老後資金をより多く確保可能。
•税金は「雑所得」として課税されます。
税金の計算と手取り額
個人年金保険の受け取りには税金がかかり、
その課税方法によって最終的な手取り額が変わります。
雑所得として課税される場合(年金形式)
【65歳から10年間の場合】
必要経費(支払った保険料に対応する部分)は88万457円。
差し引き後の所得金額は91万9,543円。
税引き後の手取り額は約1,661万円。
【70歳から10年間の場合】
必要経費は同じく88万457円。
差し引き後の所得金額は137万286円。
税引き後の手取り額は約2,043万円。
一時所得として課税される場合(一括受け取り)
【65歳で一括の場合】
必要経費として支払った保険料880万4,574円と特別控除50万円を
差し引いた残額を1/2した279万981円が所得金額となります。
税引き後の手取り額は約1,442万円。
どれが一番お得なのか?
手取り額だけを見ると、70歳から10年間年金形式で受け取る方法が最も有利です(約2,043万円)
次いで65歳から10年間(約1,661万円)、最も少ないのは65歳で一括(約1,442万円)となります。
ただし、一括の場合は税率が低く抑えられるため、一度にまとまった資金が必要な場合には適した選択肢です。
住民税非課税世帯への影響
個人年金を毎年受け取ることで所得が増え、
住民税非課税世帯から外れる可能性があります。
非課税世帯には介護費用や医療費負担軽減など多くのメリットがあるため、
一括で受け取った方がトータルで得になる場合もあります。
公的年金との組み合わせ
公的年金を5年間繰り下げて受給すると42%増額され、
生涯支給されます。一方、個人年金では5年間遅らせても増加率は25%です。
そのため、一括で個人年金を先に受け取り、公的年金開始まで生活資金として
活用する方法も検討できます。
まとめ
個人年金保険は老後資産を計画的に準備する優れた手段ですが、
自分自身や家族のライフプランに合わせて最適な選択肢を選ぶことが重要です。
以下を考慮して決定しましょう!
1.手取り額だけでなく、自分や家族の生活設計や必要資金に応じた方法を選ぶ。
2.税制上のメリット・デメリットや住民税非課税世帯への影響を理解する。
3.公的年金とのバランスを考慮し、一括・分割どちらか適した方法を選ぶ。
長期的視点で計画的に活用すれば、大切な老後資産として役立てられるでしょう。
ライフプランに合わせた受け取り方について、専門家への相談も有効です。